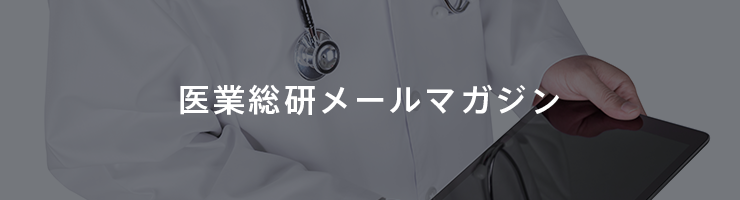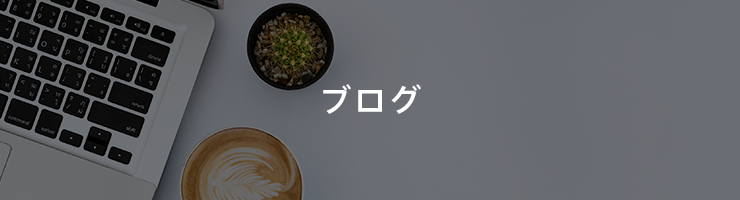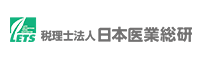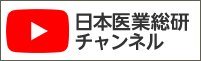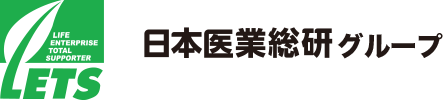「泌尿器科疾患」でキーワード検索をすると、患者数が増加傾向にあること、とくに前立腺がんが過去20年で8倍になるなど、インパクトのある数値が目に留まります。診療現場でも増加の実感値はありますか。
私が紀南病院の泌尿器科に入局した2008年当時から、ある程度推論されていたことです。実際に、男性のがんの罹患率においては、2020年を境に前立腺がんが大腸がんを抜いて一番多くなりました。人口が減少に転じたなかでの比率の変化はともかく、高齢化が総数を押し上げていることは確かにあるのでしょうね。
泌尿器科医というと、外来での検査・診断から治療、手術まで一人の担当医師が完結させるというイメージがあります。
消化器、呼吸器、循環器など内科・外科に明確に区分されているのに対して、検査から手術までという医療の一貫性はあります。
手術にしても、かつての開腹手術から腹腔鏡手術へ、さらにロボット支援化手術へと目覚ましく技術が進歩してきた領域でもありますね。
私の世代が丁度過渡期だったように思います。開腹の時代を経験し、腹腔鏡に移行、さらに和歌山県立医科大学附属病院、紀南病院、市立岸和田市民病院でダ・ヴィンチの導入を経験してきました。

全医師数に占める泌尿器科医の割合が2.4%、約8,000人といわれる一方で、高齢化に伴う患者増。現場の負担感は大きいのではないですか。
大変といえば大変ですが、地域や施設にもよるでしょうね。ハイボリュームセンターに手術を集中させて、病院間の医療機能分化に取り組んでいる地域もあります。和歌山県は相当広いのですが、高速道路が整備されたことで、医師も患者さんも移動が楽になりましたので、広域な連携が可能となっています。
膀胱炎や尿路結石など、再発の恐れがある泌尿器科疾患について、予防の概念はあるわけですよね。
もちろんです。生活習慣病と尿路結石は深く関係しているといわれていますし、BMIの高い方は痩せた方が尿路結石の再発予防に有効です。そうした予防への促しは病院でもやってきましたし、クリニックでもパンフレットを渡して説明するようにしています。
泌尿器科医が少ない、つまり泌尿器を専門に診るクリニックも地域から必要とされているわけですが、勤務医時代から開業を意識されていたのですか。
そんなことはなかったのですが、生活スタイルに変化があって、家族で話し合った結果です。ですから、開業を考え始めたのも2年前位でしょうか。

当院は、先生の義母様が経営されている医療法人マイクリニックの分院という位置づけですが、それもご家族で話し合った結果ということですね。
前面道路を挟んだ正面が本院のマイクリニック(小児科・新生児小児科)で、当院は元々本院の駐車場だった敷地を利用して建てたものです。診療科としての連続性は子どもの夜尿症程度で、多くは望めませんが、本院に導入されている血液検査機器を使わせていただいています。当日結果を患者さんに伝えられるので、そこは助かっています。また逆に、本院の小児科にはレントゲン装置が導入されていませんので、当院で子どものレントゲン撮影をするといった連携を図っています。
開業前の約1年間、済生会和歌山病院の内科に勤務されていましたが、この内科の経験も開業を意識されての選択でしょうか。
当初は、開業までの一時的な居場所という動機だったのですが、済生会の内科は、もうしばらく勤務していたかったというくらい面白かったですし、勉強にもなりました。結果的に、開業後のいまも円滑な連携が図られています。
標榜科に内科を加えられたのは、泌尿器科+αの、開業戦略の一つだったのでは?
それは多少ありますね。手術ができない分、クリニックが提供できる医療には限界があります。ただ、地域医療の前線に立つ以上、自院開業で病院外来とは違った意味でのきめ細かさは持ち合わせたいと思っていますし、通院が困難な方には、私の方から訪問しようと思っています。

当社、日本医業総研は、平松政高先生(ひらまつクリニック院長)からのご紹介でしたね。
そうです。紹介者の平松先生は大学の同期の間柄なのですが、医業総研ホームページに掲載されている大島純平先生(おおしま泌尿器科院長)も元同僚で開業インタビュー記事も読んで、コンサルを依頼しました。
他のコンサル会社とは、比較されなかったのですか。
身内のような開業医が二人いれば依頼の動機は十分でしょう(笑)。
泌尿器科ですと、女性患者さんも少なくありませんよね。
直近の患者さん30人を見ると、男性22人、女性8人になっています。比率としては、泌尿器科の平均値でしょうか。最初のうちは女性の尿失禁の方がチラホラと来られたことで、やや多めという印象でした。当院は新しく、施設もきれいなので、若い女性が比較的来院しやすいという特徴があるかもしれません。若年者の膀胱炎患者さんも多いです。

女性の場合、友人にも相談しにくいデリケートな悩みや辛さを持たれている方もいらっしゃると思います。特に気を遣われるところはありますか。
とくに女性だからと意識していることはありませんが、岸和田市民病院に勤務していたころ、腹圧性尿失禁の女性に骨盤底筋トレーニングを指導してきました。骨盤底筋の筋肉群を鍛えることで尿漏れや臓器脱などの予防・改善に効果があるとされているものです。そうした医療サービスは当院でも踏襲していきたいと考えています。
先生の診療スタイルとして、どのようなことに心掛けていますか。
的確な診断は当然のことですが、治療をせずに放置したままだと、こんなリスクがあるという要点を分かりやすい言葉でお伝えするようにしています。
がんなど、重症が疑われるケースでは、どのように対応されていますか。
まだ、開業したばかりでケースとしては少ないのですが、前職の済生会和歌山病院が近く、良好な連携関係にありますので、CTは済生会にお願いしています。当院でできる検査はある程度限られていますので、必要性に応じて早めに紹介に出すことが、患者さんにとってもいいことだと思っています。

オープニングは受付、看護師ともに2名での体制ということですが、採用ではどのような基準を設けられたのですか。
医療従事者としての人柄は重視しましたが、とくに高いハードルを設けたわけではありません。応募者自体がやや少なかったのですが、頼りになりそうな看護師と、医療事務経験のある受付を採用することができました。いまはまだ患者数が少ないので、問題なく回っていますが、増えてきたときにどうなるのかですね。開業後は、不定期ですが、メーカーの担当者に来ていただき、ランチを兼ねた勉強会を開いています。お弁当を出すこともあってか、シフト外のスタッフも含め、参加率はほぼ100%です(笑)。
内覧会の様子はいかがでしたか。
来場者は200人を超えたと思います。一部の方ですが、診察予約もしていただきました。
前立腺がんも早期発見・早期医療介入が大事だと思われます。当院では、前立腺がん早期発見の啓蒙や検査を実施するお考えはありますか。
ご存知のとおり、一般的な人間ドックでのPSA検査はオプションで追加しなければなりません。前立腺がんは、見つかっても進行が遅いということが優先順位に影響しているのかもしれません。積極的な働きかけはしていませんが、ホームページで定期的な検診を呼びかけ、利用者の反応を見ている段階です。

診察のある月曜~金曜の13:00~15:00を訪問診療に充てているのですね。
訪問診療を実施するからには看取りまで責任をもって診ていくつもりです。地域の訪問看護事業者やケアマネジャーも、当院に挨拶に来てくださいました。ただ、前職でも経験してきましたが、患者さん本人が家に帰りたいと希望されても、受け入れるご家族が施設を利用されるケースが多くあります。もちろん、老々介護の過分な負担という現実の事情もあるでしょう。私の祖母もそうでした。私としては、訪問診療を希望される患者さん、ご家族の希望を最大限に尊重し、適切な医療サービスの提供に努めていくのみです。
今回の開業は、弊社の山下明宏が担当させていただきましたが、サポート内容はいかがでしたが。
この場所で開業することが前提でしたので、他の開業コンサルとはやや事情が異なると思いますが、私からの細々とした質問に、適宜素早く対応をしていただけました。友人医師からの紹介ということで、最初から不安はありませんでしたが。
担当コンサルの山下さんは、今回の開業を振り返っていかがですか。
地域の調査や泌尿器科の診療圏分析で、必ずしも良好な数値が得られたわけではなく、完全な落下傘開業だったらどうなのか? という疑問はありました。それでも、地域での信頼の高い医療法人マイクリニックの分院ということで、グループ一丸の力が発揮されました。泌尿器科のニーズは確実にありますし、アクセスも良好なので、確実な増患が見込まれると思っています。
院長プロフィール
院長 楠本浩貴 先生
医学博士
日本泌尿器科学会認定 専門医・指導医
泌尿器腹腔鏡技術認定医
ロボット(da Vinci)手術認定医
身体障害者認定医(ぼうこう直腸機能障害)
緩和ケア研修終了
ボトックス講習・実技セミナー修了
2006年 島根大学医学部 卒業
紀南病院 初期研修
2008年 紀南病院 泌尿器科 医員
2010年 和歌山県立医科大学附属病院 泌尿器科 学内助教
2015年 和歌山ろうさい病院 泌尿器科 医長
2017年 紀南病院 泌尿器科 医長
2020年 市立岸和田市民病院 泌尿器科 医長
2023年 新宮市立医療センター 泌尿器科 部長
2024年 済生会和歌山病院 内科 医長
2025年 本町クリニック泌尿器科・内科 開設
和歌山県立医科大学 泌尿器科 博士研究員