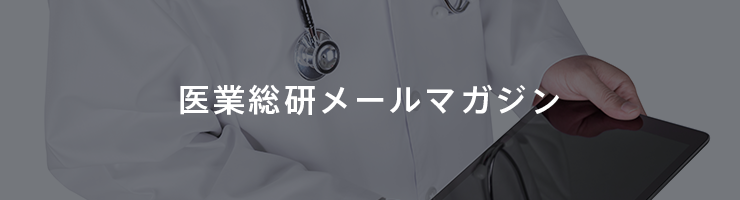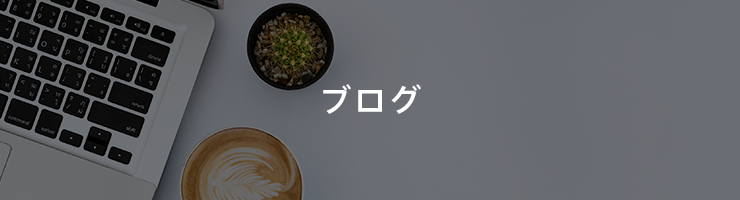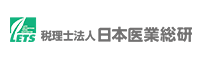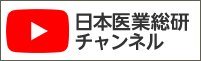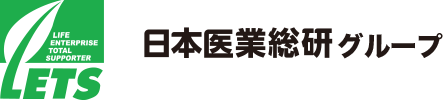子どもと同じ目線の高さで向き合う
川村先生は、お父様が開業医でいらっしゃったのですね。
すでに引退しておりますが、60歳になってから宿願の開業をかなえ、終末期医療に取り組んでいました。
お父様の姿は、先生が医師を目指すことのきっかけになりましたか。
特別な意識というより、多分、日常的に刷り込まれた医師のイメージがあるのでしょうね。開業後も、患者さんに何かあった際には、夜中の2時、3時であろうが駆けつけることがありました。それが医師としてのあたりまえの行動であることを見てきて、少なくない影響はあったように思います。
川村先生が小児科医療に進まれた動機をお聞かせください。
動機といえるような、明確なエピソードがあったわけではありません。ただ、医学部に進学する前から、医師になるのなら小児科だろうと思っていました。

当社、日本医業総研は、お父様からの紹介ということですね。
以前、父が経営の相談で日本医業総研の猪川さん(同社代表取締役)と面識があったようで、開業で悩んでいるのならここに電話したらどうかと名刺を預かったのがきっかけです。ホームページを見ると、知り合いの医師も何名か医業総研の開業支援で成功していることから早速コンタクトを取り、今回担当いただいた山下明宏さんとの面談となりました。
他のコンサルティング会社とは比較されなかったのですか。
しませんでした。というよりも、開業や経営のノウハウなど何もないなかで、どこに相談すべきかの判断もつきません。他社の勉強会には受講登録はしていたのですが、結局参加しませんでした。父の印象と持っていた名刺に頼ったということです。
開業にあたり、クリニックの特徴や先生の強みをどう発揮しようとしましたか。
小児科に関しては、何よりも、私自身、子どもが好きだということ。それと、昔から何かしら人のお役に立ちたいと思ってきましたので、患児やご家族の気持ちに寄り添えることが一番の強みかなと思っていますし、それこそが開業で一番やりたかった医療です。

子どもは自分の意思で受けたい医療を選べません。そこで、来院した子どもに与える安心感と、保護者との信頼関係が大事になってくるわけですが、コミュニケーションの部分でとくに気をつけていらっしゃることは何でしょうか。
目線を同じ高さにすることは意識しています。たとえ子どもであろうと、医師と患者さんは対等であらねばなりません。とくにお子さんと喋るときは、お子さんの目線までこちらの目線を下げることで、子どもと正面から向き合っている医師なのだということを親御さんに実感して安心いただけるのではないかと思っています。
子育て不安を抱かれるお母様方からの相談もありますね。
そうですね。とくに小さなお子様であれば離乳食の進め方であったり、少し大きくなると、今度は学校生活の悩みなどメンタルの不調を訴えるケースも多く、子どもとどう接したらいいのかというような悩み相談を受けることがあります。
悩みがメンタル領域に及ぶと、明確な解答は難しいですよね。
すごく難しい。大学の教科書には載っていないことですし、指標となるエビデンスがあるわけでもありません。結局、私の子育て経験と反省を踏まえながら話をさせていただくのですが、メンタルの問題にどこまで寄り添うことができているのかには、やや悩ましいことがあります。

小児科クリニックでのコミュニ―ション能力は、看護師や受付スタッフにも強く求められますが、採用ではどういった点を重視されましたか。
私と同じように、子どもと同じ高さの目線で接し、子どもと遊ぶことができる人、同時にスタッフ間での円滑なコミュニケーションが図れる人です。限られた面接時間でそれを判断することは難しいのですが、これまでの職歴で子どもたちにかかわってきたり、小児科医療に携わってきた方を中心に採用しました。
そうして採用されたスタッフについて、チームワーク向上や小児科医療従事者としてのスキルアップのための活動は実施されていますか。
定期で行っていることはありませんが、何かしらの問題・課題が生じたときは、その都度、全員で解決に向けたディスカッションをするようにはしています。
開業から約2年が経ちました。病院勤務医とは違う、川村先生なりの小児科外来スタイルは確立されましたか。
確立とまでは、まだ言い切れません。お子様一人ひとりの訴え、親御さんの悩みに十分傾聴して解決の糸口を探ることができれば、もっとしっかりと治療することは可能だと思いますが、現状の患者数で、そこまでの十分な時間が割けないというのが正直なところです。「こうしてあげたい」という私の思いを、短時間でいかに効率よく伝えるか。そこにまだまだ改善が必要です。

個々のライフスタイルに合わせて治療アプローチをカスタマイズ
先生のもう一つのご専門であるアレルギーですが、国民病といえるほど罹患者が多く、花粉症の低年齢化傾向などもみられます。アレルギー疾患の治療は長期にわたるものが多いわけですが、患者さんのなかには自己判断で治療を中断してしまうケースもあるようです。根気強く治療を継続していただくために、どのようなアドバイスをされていますか。
なるべく、患者さん自身が続けやすい治療を選択するというのが1つですね。ガイドラインで望ましい治療が示されていても、それが患者さんのライフスタイルに噛み合わなければ、離脱されてしまう可能性が高くなります。基本的にはガイドラインに従いますが、毎日の起床時間、通勤状況、勤務時間、帰宅時間、その他の生活リズムに則した処方や、投薬の回数など治療を継続しやすいようにカスタマイズすることもあります。

アレルギー症状の原因は遺伝子傾向や環境要因だったりするわけですが、発症以前の予防という考えはあるのでしょうか。
いまアレルギー分野のトピックはまさに「予防」であり、学会などでも盛んに議論されています。アレルギーの基本に、肌から始まるという考え方があります。私は小児科医なので、乳幼児のころから診ていくことが多いのですが、ご両親にアレルギーがあると子どもは体質的に発症しやすくなりますから、常に肌をキレイに洗い保湿剤をしっかり塗ることを徹底しながら、予防策を講じるよう話をしています。予防は、年齢を重ねるにつれ難しくなりますので、発症の前段階から対策を講じることが大切です。
先生は、大学も含め、兵庫県、大阪府での生活が長く、ご自宅も大阪市内ということですが、当初より開業するのなら生まれ故郷の京都でとお考えだったのでしょうか。
大阪の方が立地の選択肢も多かったのでしょうが、それでも京都に帰りたいという思いが強くありました。
(山下明宏/日本医業総研)京都での開業希望はうかがっていましたが、私は先生の通勤の負担を心配していました。ご自宅から電車を乗り継いで1時間強かかりますから、体力的にどうなのだろうと、物件選定でもずっと気にかけていました。
(川村先生)全然苦ではありません。毎朝、息子と一緒に起きて、電車に乗っています。最近運動不足気味なので、途中で降りて3駅分、3kmくらいでしょうか、毎日歩くようにしています。
クリニックの動線で特徴的なのが、感染症が疑われる患者さんの入り口を別に設けられていらっしゃいます。開業が2023年ですから、新型コロナを意識された部分もあるのでしょうか。
必ずしもコロナがきっかけだったわけではなく、インフルエンザも含め、入り口を分けることは小児科クリニックを新設するうえでの必須条件として考えていました。昔の小児科は、1カ所の出入り口で、せめて受付を分けることが普通でしたが、今の時代は、万全な感染症対策がないことを気にされる方もおられるだろうと考えました。

立地選定のポイントは、アレルギーへの専門性
2023年の開業から順調に経営を伸ばし、すでに医療法人成りの準備に取り掛かっておられるようですが、この短期間での成功をどのようにとらえていますか。
成功かどうかの判断基準はさておき、やはり山下さんの情報収集力と、そこで紹介いただいたこの物件ですね。私たちがどれだけ頑張ったところで、ベースに子どもがいなければ話になりませんから。阪急桂駅のショッピングモール「ミュー阪急桂」で、同じフロアに調剤薬局を併設したドラッグストアもあることから、比較的早期に地域から認知されたように思います。それと、患者さんに寄り添う医療という経営理念をスタッフ全員がキチンと理解し、実践しようと頑張ってくれたおかげだと思っています。
今回の開業では、株式会社日本医業総研の山下明宏がコンサルを担当し、開業後の税務・会計業務を税理士法人日本医業総研の栗原大樹が担当させていただいております。当社グループのサポートは先生のご期待にかなうものだったでしょうか。
開業については、何も前提となる知識がなく、「社保」「国保」の違いすら分かりませんでした。施設基準なども同様です。そうした状況下で、山下さんには練り込まれた事業計画と物件選定、各種業者の手配、届出関係などまでお願いし、完璧に仕上げていただき、感謝しきれないほどです。税務・会計の栗原さんにも毎月訪問いただいていますが、月次の収支管理、確定申告なども含め万全のフォローをしていただき、本当に助かっています。

山下さん。川村先生は今回の物件選定を成功要因の一つとしてあげられていましたが、立地選定では、どういったポイントを重視されたのですか。
(山下)一般的な小児科クリニックの開業セオリーでいうと、住宅街で日常的に利用する商業施設の近くや、複数台の駐車場が確保された郊外などが候補エリアとなります。ですから、当院が1日100人の子どもを診る小児科オンリーだったら、この物件を提案することはなかったでしょう。私が着目したのは、川村先生はアレルギーの専門医でもあり、子どもから大人まで幅広い患者層で豊富な治療業績をお持ちだという点です。患者さんの年齢層が広がるだけでなく、駅ビルであれば通院の利便性の高さから、広域からの集患が期待できます。実際、アレルギーでかかる患者さんも増加傾向にあるようですし、潜在ポテンシャルはまだまだ高く、十分な伸びしろがあると確信しています。
院長プロフィール
院長 川村 孝治 先生
日本小児科学会 専門医
日本アレルギー学会 専門医
エピペン処方医
舌下免疫療法 受講終了医師
2009年 兵庫医科大学医学部医学科 卒業
恩賜財団大阪府済生会泉尾病院 初期研修医
2011年 市立伊丹病院 勤務
2013年 大阪大学医学部付属病院 勤務
2014年 市立伊丹病院 アレルギー外来
2023年 小児科・アレルギー科かわむらクリニック 開設